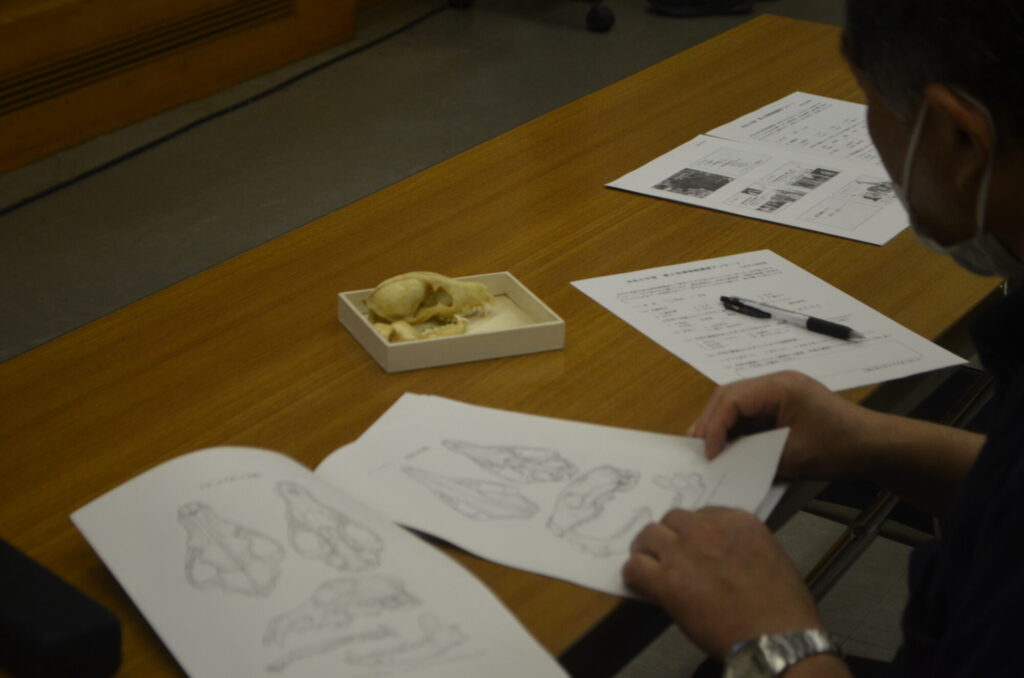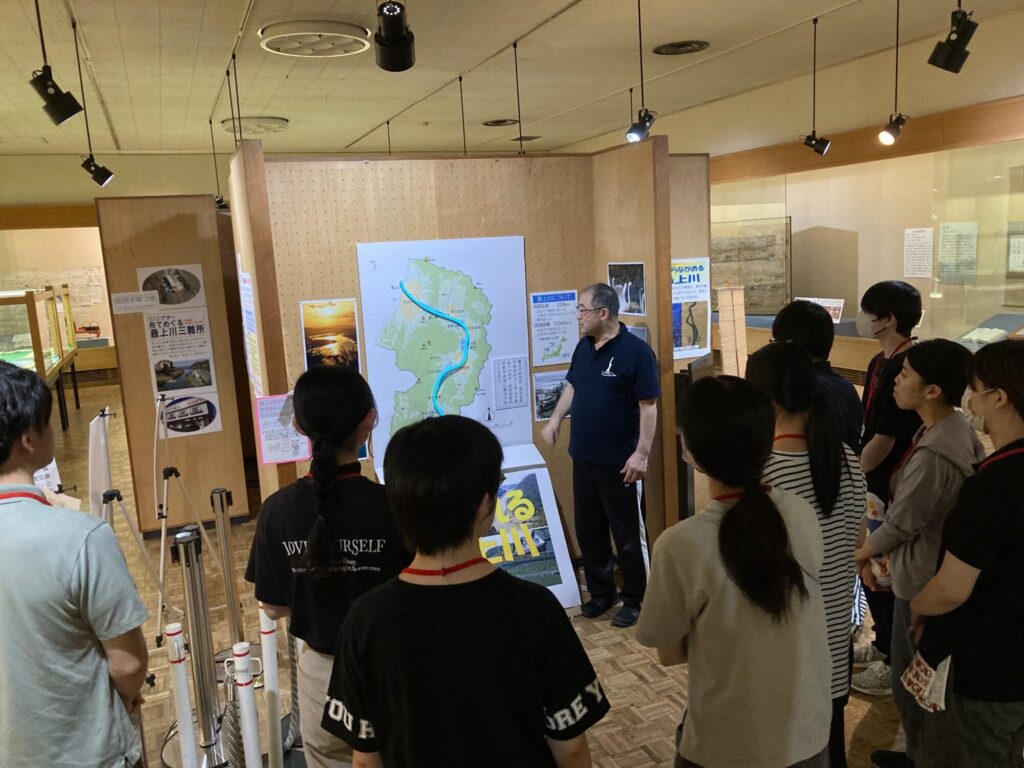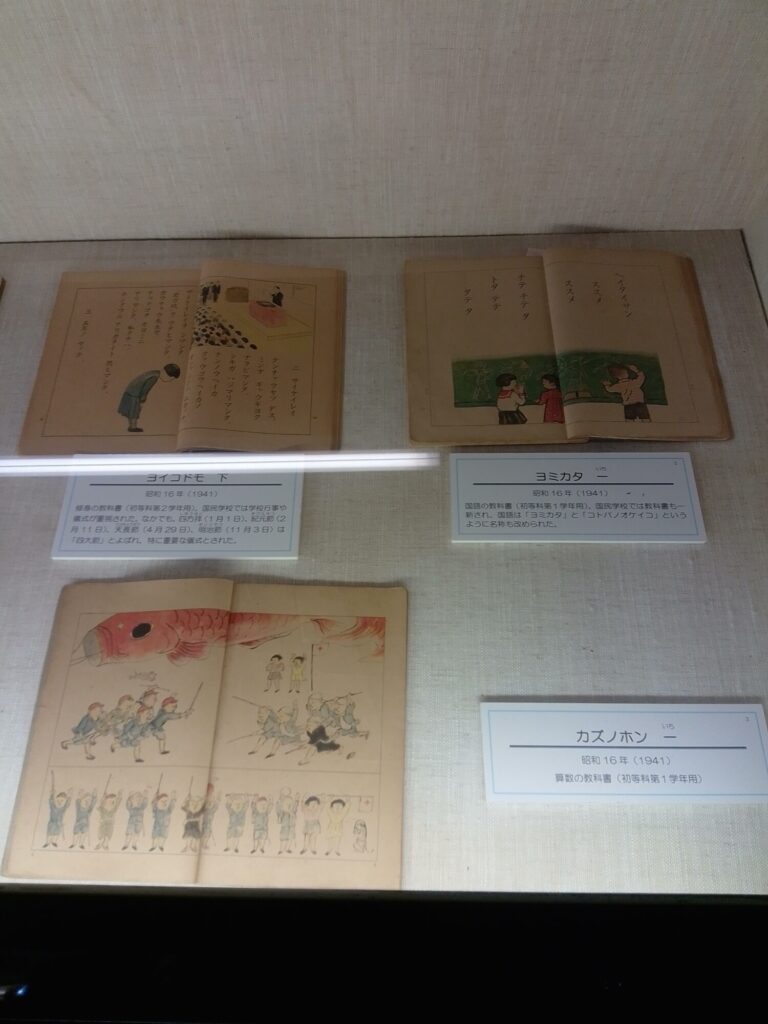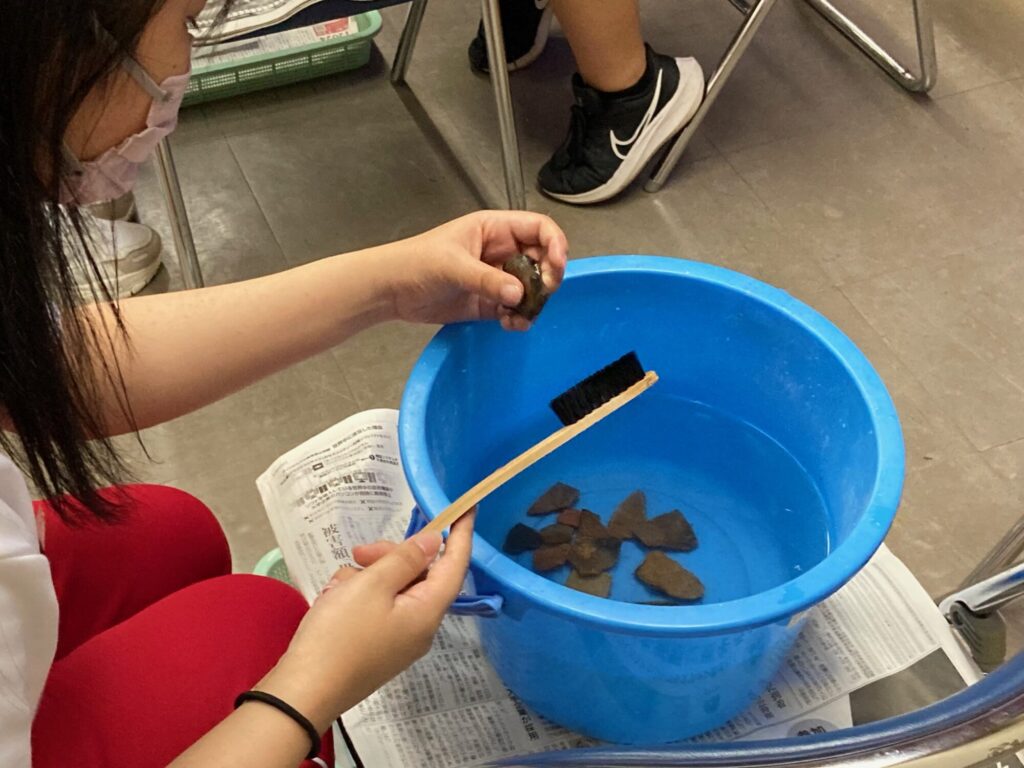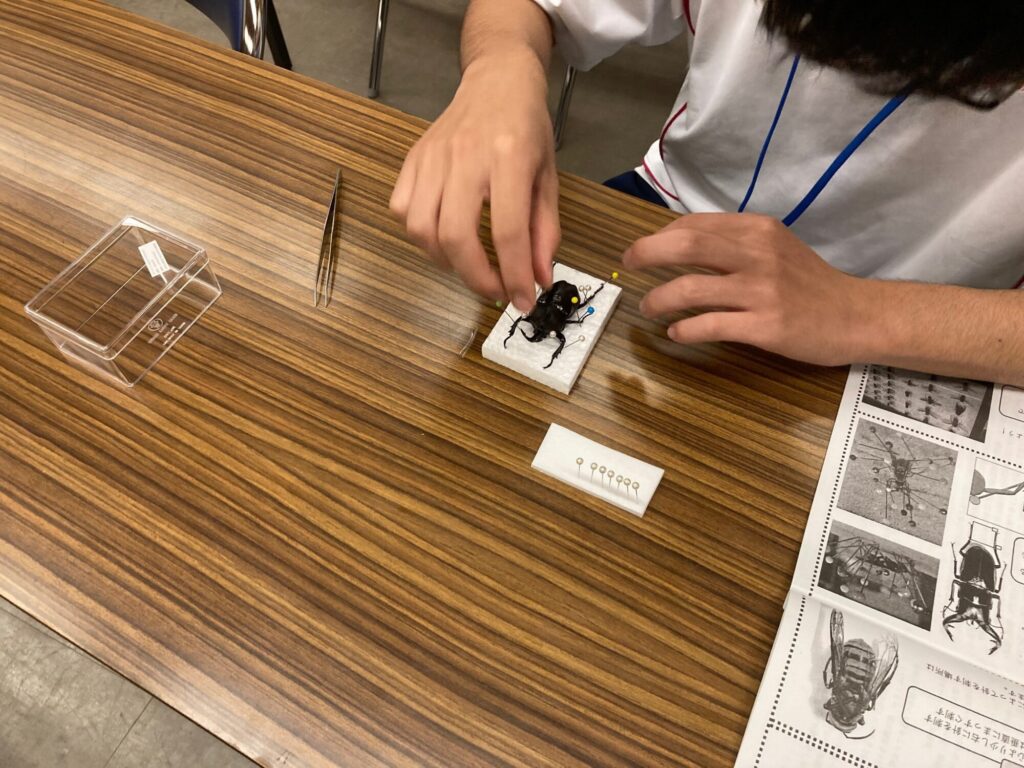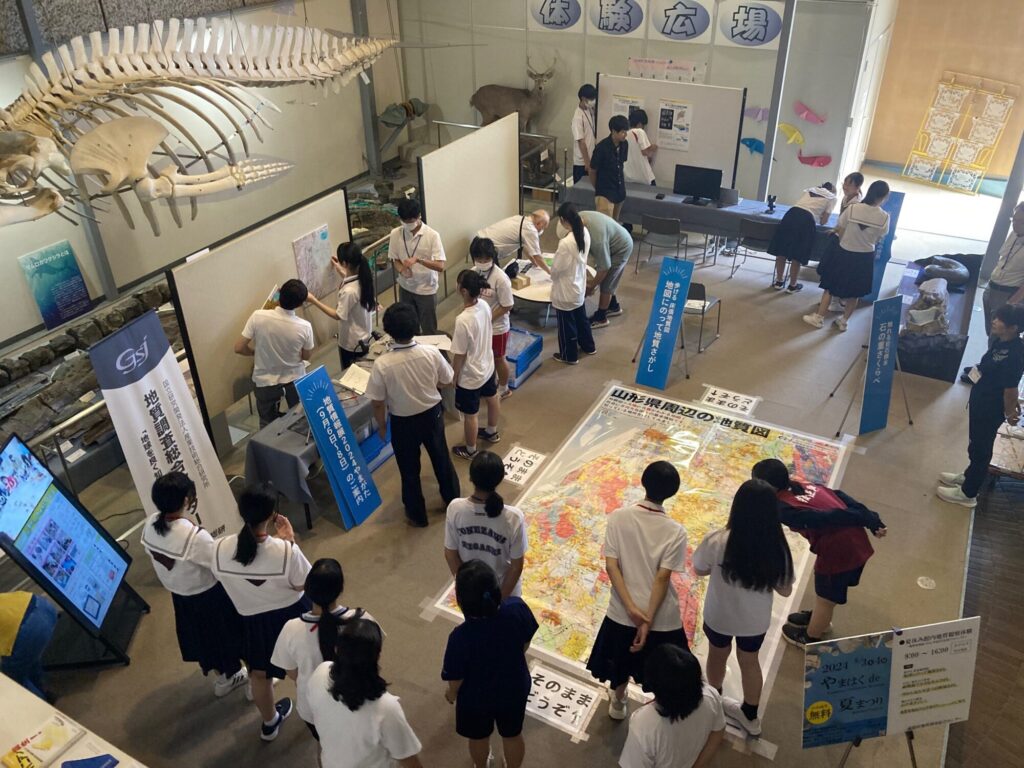冬は火災のリスクが非常に高まる季節です。国の重要文化財に指定されている教育資料館では
毎年1月下旬に火災を想定した総合的な消防訓練を実施しています。
今年は1月29日(水)10時から実施予定です。当日来館されたお客様には避難訓練に参加して
いただく場合がございますので予めご了承くださいませ。
教育資料館職員と博物館本館職員が合同で訓練を行います。
山形市消防署員の立ち会い指導の下、避難誘導・通報の演習と屋外消火栓を使用しての
放水訓練など様々な訓練を行う予定となっております。


上記の写真は敷地内に設置されている屋外消火栓です。
近年の消火栓とは異なる珍しいデザインをしているのでご紹介させていただきました。
とてもレトロな見た目をしていますよね。
そして毎年1月26日は「文化財防火デー」に制定されています。
出火防止対策を徹底することはもちろんですが、万が一火災が発生した際に被害が最小限で済むよう
日頃から防火意識を高め、貴重な文化財をみんなで守っていきましょう。
◇ 資料館からのお知らせ
1/29(水)10:00~ 消防訓練実施
冬の資料館はとても寒いので防寒対策をしっかりしてお越しください。
本年もたくさんの方のご来館を心よりお待ちしております。